|
四 季 雑 感
(11)
口蹄疫の流行を憂う
牛の病気の口蹄疫が問題になっている。牛ばかりではなく蹄が二つに割れている動物は皆感染の心配がある。従って馬は対象にならないのが不幸中の幸いだ。人間には感染しないと言うけど、その怖さは数年前に流行った鳥インフルエンザとは比較にならない。強烈なウイルスが飛び回り一度付着すると確実に感染し、症状は口の周りに出来物ができるのだけど、このために餌が食べられなくなってやせ細り、最後は肋骨が浮き上がり、骸骨のようになって死んでしまう。アルゼンチンにいるときに、それまで全く知らなかったこの病気の恐ろしさを教えられた。主食が牛肉であり、輸出品の重要な品目でもある牛のことに関しては、日本とは比べ物にならないくらい神経質である。日本人も、これからも、”しゃぶしゃぶ”や”すき焼”、とんかつが食べたいのなら、もっと関心を持たないといけないと思うのだが。そんなアルゼンチンで次のようなエピソードを聞いたことがある。ただし、この話が本当かどうかは知らない。 『第二次大戦が終わった頃、米国は南米の口蹄疫の伝染をおそれ、中北米地域ではこの病気を絶滅しようと計画し、メキシコからパナマとコロンビアとの国境までの中米地峡一帯の農家を一軒づつ当たり、疑いのある牛は全部買い上げて処分した。この結果、パナマからカナダまでの中北米には口蹄疫の牛は一頭もいなくなり、安心できるようになった』 ということである。パナマとコロンビアの間は、ダリエン地峡といって一番細くなっている湿地帯である。苛酷な湿地帯のため道路ができないと言われている。アラスカからチリのプエルト・モンまでを結ぶ、ケネディ大統領が作ったパンアメリカン・ハイウエーも正確にはここで一旦途切れている。このため人間を始めすべての動物は歩いて通ることはできない。南米と中米間の交通は船か飛行機しかない。道路を作らないのは、米国の戦略的思惑があるのかもしれないが、いずれにせよ、ここで南米の口蹄疫を持った四脚の動物は北上を遮断されている。米国にしてみればこれで安心というわけだ。 もっとも今では、南米の国々でも口蹄疫は殆んど無くなったと思うが。 牛の話が主なので、世界で一番牛肉を食べる国と言われるアルゼンチンで聞いたり見たりした話を書いてみようと思う。 アルゼンチン人は朝飯から牛肉を食べる。成人一人の一回の平均は400〜500グラムで、焼き上がりの大きさにすると厚さ3センチで長さ15〜20センチ位ある。こ 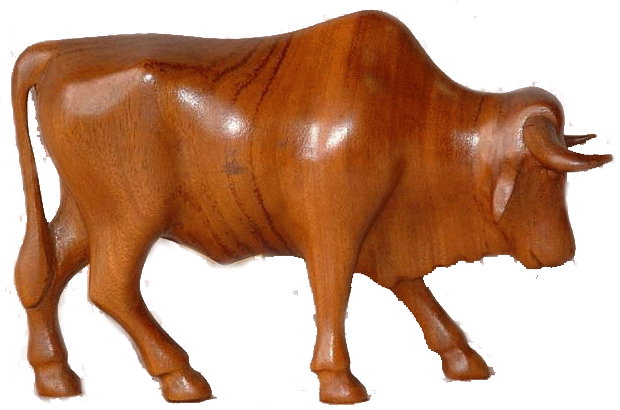 の内五分の1くらいは脂肪なので赤肉は300〜400グラムだが、初めてお目にかかると、その大きさに度肝を抜かれる。そして日本人なら誰でもが、こんなものを全部食べたら、胃がもたれて消化薬を飲まないと大変だ、と心配する。ところが、どうしてどうして、肉ほど消化の良い食べ物はないと言っても言い過ぎではないのだ。私も初めの頃は日本製の消化薬を余分に飲んでいた。その後現地の人間にアドバイスされ、思い切って消化剤を飲まないで我慢した。翌朝は胃のことを全く意識しないほどに胃が軽かった。消化が良いのは本当だったのだ。消化が良いことの証拠の一つが、牛肉のヒレ肉は幼児の離乳食や病人の食材になっているということである。厚さ4,5センチに切ったヒレの周りを焼いて、まだ血の残る中央部をスプーンですくって食べさせる。味付けはほんの少々の塩だけだ。一度夕食に腹一杯食べてそのまま寝てみてはどうだろう。肉を見直すかもしれない。
の内五分の1くらいは脂肪なので赤肉は300〜400グラムだが、初めてお目にかかると、その大きさに度肝を抜かれる。そして日本人なら誰でもが、こんなものを全部食べたら、胃がもたれて消化薬を飲まないと大変だ、と心配する。ところが、どうしてどうして、肉ほど消化の良い食べ物はないと言っても言い過ぎではないのだ。私も初めの頃は日本製の消化薬を余分に飲んでいた。その後現地の人間にアドバイスされ、思い切って消化剤を飲まないで我慢した。翌朝は胃のことを全く意識しないほどに胃が軽かった。消化が良いのは本当だったのだ。消化が良いことの証拠の一つが、牛肉のヒレ肉は幼児の離乳食や病人の食材になっているということである。厚さ4,5センチに切ったヒレの周りを焼いて、まだ血の残る中央部をスプーンですくって食べさせる。味付けはほんの少々の塩だけだ。一度夕食に腹一杯食べてそのまま寝てみてはどうだろう。肉を見直すかもしれない。アルゼンチンは人口3300万人なのに牛が6500万頭もいる(この数字には色々な統計がある)。人口の倍以上もいる牛はパンパ(草原)でのんびりと飼われている。環境が牛の肉質に影響を与えているのは確実である。南米南部の地勢はアルゼンチンからウルグアイ、ブラジル、パラグアイにかけて緩やかな上り傾斜で、果てはアンデスやブラジルの高地に続いている。傾斜地の牛は牧草を求めて上下に動き回るので、体の筋肉が締って硬くなる。それに反してアルゼンチンの牛は、牧草が豊富な大平原の牧場で、自分の足元の草だけを1日掛けて食べる、24時間で自分の位置を一回りすれば十分なのだ。餌は栄養十分なアルファルファ(日本名:うまごやし)である。歩き回る必要がないので筋肉は柔らかい。アルゼンチン人が ”俺の国の肉は世界最高だ”と自慢するのもむべなるかなである。何十頭もの牛が常に同じ方向を向いて草を食べている光景は、気がつかなければ何とも思わないが、気にすると何故いつも同じ方を向いているのか不思議でならなくなる。パラグアイへ行ったとき、遠くから見て骨っぽい姿からてっきり馬だと思ったのが近寄って牛だと分かった時は、こんな牛を食べるパラグアイの人たちが気の毒に思えたものである。 あるとき公共事業省の高官を家へ呼んで食事をした。妻が材料をやりくりして天ぷらを揚げた。日本酒も出した。そして、宴もたけなわを過ぎデザートになるころ、これに肉があると最高だねと一人が言った。彼らはなにを食べても最後は肉で締めないと食事の終りにはならないのだ。 日本人の肉の食べ方について、アルゼンチン人の食べ方との違いを考え、現地の人の意見も聞いてみた。そして一つの仮説ができた。それは、『日本人を含め東北アジアの国々は寒い季節が長いので、餌になる草の育つ期間も短く量も充分ではない。そのため牛の数も少なめだし、肉も比較的固めで値段も高いのでアルゼンチン人のような食べ方はとても真似できない。そこで、少量の肉で満足する食べ方を考え出した。それが、”すき焼”とか”しゃぶしゃぶ”とか、炒めたり、刻んだり、ほかの食材と混ぜ合わせたりして味を濃くするやり方である。要するに少ない量でも肉を食べたと思へるような調理方法が生まれたのだ』。という結論である。一方、アルゼンチン人は500グラムもある肉に特別な味付けはせず塩だけである。レモンを絞るのは鶏肉の時だけだ。濃い味だととても500グラムは食べられないだろう。しかしアルゼンチンにいる日本人は塩だけではやっぱり物足りないので、携帯用の醤油瓶を持ち歩いていた。これを数滴たらすのが最高の味だったことを懐かしく思い出す。 肉を食べるときの特徴の一つに、野菜の量が少ないことがある。エンサラーダ・ミスタ(ミックスサラダ)と注文すると、キャベツ、玉ねぎ、トマトが軽く盛られた普通のお茶碗くらいの食器が出てくる。もし火を通せば一口の量である。とても足りないので慣れてからは常に2人分を注文するようになった。野菜の摂取量が少ないから、血中のコレストロールが濃くなり、静脈が詰まったりするのだろうか、脚の血管が浮き上がっている老人を随分と見かけたものである。 口蹄疫の話から牛の話を長々と喋ってきたけど、口蹄疫は正直な話笑い事ではない。メキシコ湾の原油流出事故とどちらが先に終焉するのか、気のもめることである。日本で”すき焼”や”しゃぶしゃぶ”、トンカツが食べられなくなる日がくるのか、キューバやユカタン半島を囲むカリブの紺青透明な海が消えるのか、行方を固唾を飲んで見守っている。 (2010. 5 20 樫村慶一記, カットはパラグアイの木彫り民芸品) |